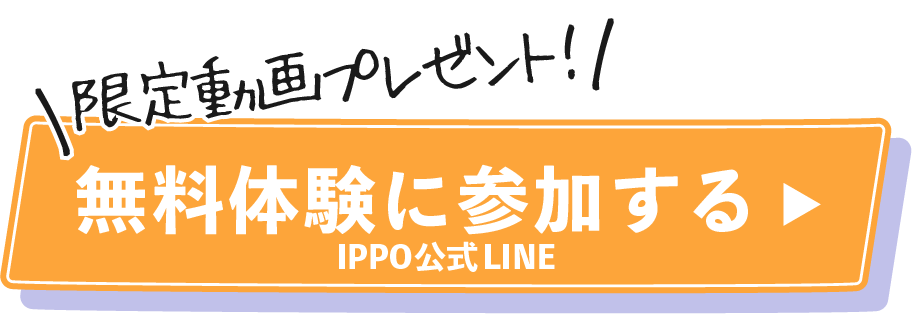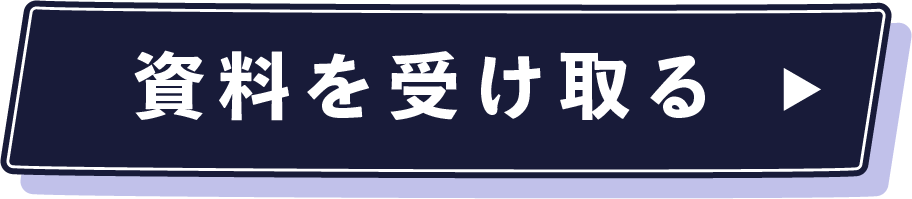サッカーの“センス”って、いったい何?
「うちの子、サッカーセンスがなくて…」
そんな言葉を保護者の方からよく耳にします。
でも、ここで一つお伝えしたいのは、サッカーの“センス”は生まれつきではないということ。
実際に、上手な選手に共通するのは、特別な才能よりも「状況を見て、考えて、判断する力」があることです。
つまり、センスの正体は“考える力”。そしてこれは、正しい練習や関わり方によって育てることができます。
この記事では、「考える力」を育てるための練習や日常での関わり方をわかりやすくご紹介します。
“考える力”は「見る力」と「判断する力」からできている
サッカーで必要な“考える力”の正体は、主にこの2つです。
- 状況を把握する力(=見る力)
- プレーを選ぶ力(=判断する力)
パス・ドリブル・シュートなどの技術があっても、それを“いつ・どこで・どう使うか”がわからなければ活きません。
逆に、技術が未熟でも判断がよければ、試合で“効いている選手”になることができます。
たとえば、こんなプレーにその力は表れます。
- 味方が出しやすい位置に早く動く
- 相手の守備のスキをつくタイミングで仕掛ける
- ピンチのときにリスクを減らすプレーを選べる
こうした「気づいて・考えて・選ぶ力」は、日々の練習の中で少しずつ伸ばすことができます。
「考える力」を伸ばす練習のコツ
では、どうすれば考える力を育てられるのでしょうか?
大切なのは、“問いかけ”と“自分で選ばせる場面”をつくることです。
たとえば…
- 1対1の練習後に「どこが勝てたポイントだった?」と聞いてみる
- パスの選択を間違えたときに「他にどんな選択があったと思う?」と一緒に振り返る
- 「この練習で意識していることは何?」と確認する
こうした問いかけは、子どもが“考えるクセ”を持つきっかけになります。
正解を教えるのではなく、考えるプロセスを大事にすることが、センスを育てる一番の近道です。
家でもできる!思考力を伸ばす関わり方
「でも、練習を見に行けないから関われない…」
そう思っている保護者の方も多いかもしれません。
でも実は、家庭のちょっとした会話でも、考える力は伸ばせます。
たとえば…
- 「今日の練習で楽しかったのはどこ?」「なんで楽しかったと思う?」
- 「試合で一番うまくいったプレーは?」「それはどうして成功したんだろう?」
- 「あの場面、自分だったらどうしたと思う?」
こういった問いかけを日常に入れていくと、子ども自身が“自分で考える”力を育てることができます。
また、保護者の方が「うまくできたかどうか」ではなく、“どう考えたか”を聞いてあげる姿勢を持つことで、子どもは安心して失敗もチャレンジもできるようになります。
まとめ:「考えるセンス」は誰でも伸ばせる
サッカーのセンスは、生まれ持った才能ではなく、考える力を育てた結果として身につくものです。
だからこそ、どの子にも伸びる可能性があります。
その力を引き出すために必要なのは、「自分で気づいて判断する」経験と、それを支える周囲の声かけ。
正解を教えるのではなく、一緒に考える時間を大切にすることが、子どもたちの“サッカーセンス”を磨いていきます。オンラインサッカー塾IPPOでは、そうした「考える力」を育てる声かけや練習を大切にしています。
自分で気づき、判断し、行動できる選手に育ってほしい――
そんな想いで、子どもたちの“考える力”を一緒に引き出しています。