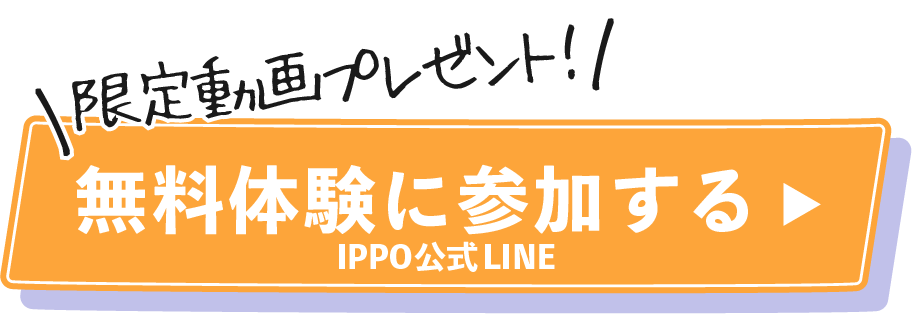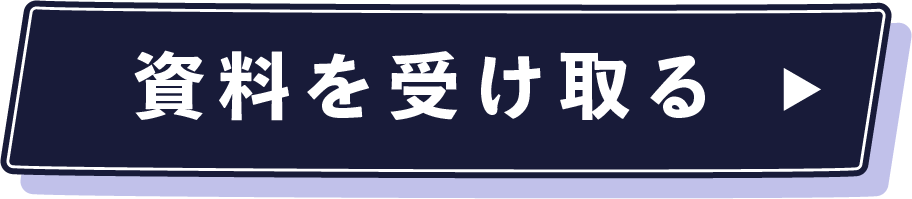「もうサッカーやめたい」と言われた瞬間、心がざわつく
突然、お子さんから「サッカーやめたい」と言われたら、胸がぎゅっと痛みますよね。
これまでの努力や送り迎えの日々を思い出して、「どうして?」と戸惑うのは当然のことです。
でもその言葉の裏には、本当にサッカーを嫌いになったわけではなく、“うまくいかない苦しさ”や“気持ちの迷い”が隠れていることがほとんどです。
「やめたい」は、“もう終わりたい”ではなく、“どうすればいいかわからない”のサインかもしれません。
この記事では、そんな子どもの気持ちをどう受け止め、再びサッカーに前向きに向き合う力を取り戻すための関わり方を紹介します。
1. まずは「気持ちを受け止める」ことから
親としては「なぜ?」「何があったの?」と理由を聞きたくなります。
けれども、最初に大切なのは、答えを探す前に気持ちを受け止めること。
「そっか、そう思ってるんだね」「最近つらかったのかな?」――
そんな一言で、子どもは「話を聞いてもらえた」と感じます。
これが“本音を話せる土台”になります。
子どもは時に、「やめたい」と言いながらも心の奥では「うまくなりたい」「もっと楽しみたい」と思っています。
その複雑な感情を整理できるように、まずは安心して話せる時間を作りましょう。
2. 「やめたい」の裏にある本当の理由を探る
“やめたい”という言葉の背景には、いくつかのパターンがあります。
- 思うように上達できず、自信を失っている
- 試合に出られず、居場所を見失っている
- コーチや仲間との関係に悩んでいる
- 周囲の期待やプレッシャーで楽しさを感じられない
これらはどれも、サッカーを続ける中で誰もが一度は通る壁です。
ただし、本人にとっては「自分だけがうまくいかない」と感じるつらい時間でもあります。
そんなときは、「どうしてやめたいの?」ではなく、
「どんなときにそう感じる?」「楽しい瞬間はどんなとき?」と問いかけてみてください。
否定せずに話を聞くことで、子ども自身が“本当に向き合いたい気持ち”に気づいていくことがあります。

3. 「やめる・続ける」ではなく、“どう関わるか”を一緒に考える
親ができる一番のサポートは、“続けさせること”でも“やめさせること”でもありません。
大切なのは、「どうすればサッカーを前向きに続けられるか」を一緒に考えること。
サッカーを続けるかどうかは、最終的には本人が決めることです。
でも、その判断を“感情のまま”ではなく、“自分に合った形で”できるように導くのが親の役目です。
たとえば、
「一度チームを休んで気持ちを整理してみる」
「ポジションを変えてみる」「練習の仕方を変えてみる」
といった選択肢もあります。
環境を少し変えるだけで、子どもが再び“サッカーって楽しい”と思えることはよくあります。
やめることを急がず、“もう一度サッカーとどう関わりたいか”を一緒に模索する時間を大切にしてください。
4. 親の「励ます言葉」が子どもの立ち直りを支える
子どもが悩んでいるとき、何よりも力になるのは「信じて見守る言葉」です。
「うまくいかない時期は誰にでもある」「今は踏ん張りどきだよ」――
そんな一言が、子どもの心に灯をともします。
逆に、「続けなさい」「やめたら後悔する」と強く言ってしまうと、プレッシャーだけが残ってしまいます。
応援のつもりが、子どもにとっては“責められた”と感じることも。
大切なのは、行動よりも気持ちを肯定すること。
「頑張ってるね」「ちゃんと考えてるね」と声をかけるだけで、
子どもは「また頑張ってみようかな」と自然に前を向き始めます。
まとめ:やめる・続けるではなく、「サッカーとどう向き合うか」
子どもが「サッカーやめたい」と言うとき、それは終わりではなく、次の成長の入り口です。
親ができるのは、「やめてもいい」と背中を押すことではなく、
「どうすればまた楽しめるか」を一緒に探すこと。
焦らず、寄り添い、考える。
そのプロセスこそが、子どもにとって本当の意味での“上達”につながります。
オンラインサッカー塾IPPOは、子どもたちが「考える力」を育て、自分らしくサッカーを続けていけるようサポートしています。
もし今、お子さんが迷っているなら、“辞めたい”を終わりにせず、“考えるきっかけ”に変えていきましょう。